Interview

テルモの未来への成長に向け、
生産技術のさらなる進化を目指す
Y.M.
技術部 生産技術課
経歴
医療分野に興味があり、大学院では薬学の研究に勤しむ。2010年、大学があった静岡の製薬会社に入社し7年間、薬の製造・生産部門で生産技術を担当。生産子会社のスタッフと連携し、プロジェクト単位で製品を創り出す現場に携わる。2016年にテルモへ転職し、技術部生産技術課ステント/バルーンチームに配属。新商品や製品増産時の設備・工程の立上げを担当し、現在はチームリーダーとして生産工程の効率化や収益改善業務、新規技術の探索などの職務に携わる。
経験・スキル
前職では医薬品生産のプロジェクトマネジメントに携わり、生産工程に必要となる工程設計・条件設定業務をはじめ、不良率削減や業務効率化につながる統計・データの分析、工程の外部移管など、品質条件を満たす薬の安定的な生産手法を多岐に学ぶ。現在は様々な生産設備のプロジェクト推進やチーム運営に携わり、前職で培った知見を活かすだけでなく、設備設置に必要な工学系の技術知見、ICTやAIといった先端領域の知見も吸収。生産効率の向上を図る自動化、省力化、新技術導入にチャレンジしている。
志望理由
前職では、長い通勤時間や膨大な仕事量、長期間の出張により、子育てや家族と過ごす時間を持てないことに悩み、それがきっかけとして転職を検討する中でテルモと出会う。医療機器業界の大手で、医療現場に貢献するさまざまな医療デバイスを製品化していることから、これまでの経験・スキルを活かして新たなチャレンジができることと、ライフスタイルに合わせ、柔軟な働き方を可能にするさまざまな取り組みや制度もあることから、ここなら自分が満足できる環境があると考え、転職を決める。


理想のワークライフバランスを
実現するために。
前職は個人プレーが中心のワークスタイルで、多大な業務負荷による残業や休日返上が常態化し、第一子の育児にも満足に携われませんでした。そのため妻から第二子を授かったと聞いた時、「同じ後悔をしたくない」と考え、転職を決断しました。すでに住宅を購入していたため、短い通勤時間の中で自分のキャリアを活かせる企業を探し、同じ医療業界で生産技術職を募集していたテルモに出会いました。ただ、前職は製造するのが医薬品であった一方、テルモは医療機器であり生産工学系寄り。機械の知識は不足していましたが、そこは「知見や経験の幅を広げるチャンス」だと捉え、入社を決めました。
実際に入ってみると、まさに想像通りの職場でした。仕事はチームプレーで問題を1人で抱え込まずにフォローし合え、自分と同じ動機や職歴を持つキャリア入社者も多いので、仕事の進め方や不足していた工学系の知識なども積極的に相談できました。また、出社が中心ではありますが、在宅勤務の活用等、業務内容・業務状況・生産性を踏まえて、最適な働きかたを選択することも可能です。第三子にも恵まれ、ワークライフバランスをとりながら、仕事にも子育てにも全力で取り組める今の環境に、大いに満足しています。
全社を横断する一大プロジェクト、
“スマートファクトリー化”への挑戦。
現在はチームリーダーとして、ステント/バルーン製品の生産設備に関するプロジェクトの推進やチーム運営などに携わっています。なかでも重点を置いているのが、生産効率・収益率向上のモデルケースとなる“スマートファクトリー化”のプロジェクト。そこでは2つの側面からアプローチしています。1つは、微細なサイズでデリケートなカテーテル製品の組み立てをいかに自動化するか。もう1つが、ICTやAI、データ解析などの先端技術で工程をいかに効率化するか。これらの課題は大きな壁ですが、幸いテルモにはチャレンジを促す文化が根付いています。チームで自由闊達にアイデアを出し合い、壁を乗り越える試行錯誤を重ねています。
スマートファクトリー化は、テルモの“未来”につながる全社横断のテーマです。私たちだけでなく、品質管理や開発、生産など関連部門のリーダーたちと積極的にミーティングを行い、最適解へ辿り着こうと知恵を絞っているところです。実はプロジェクト完了の目標があと数年先に迫っており、メンバーのタスクを定義し、マイルストーンを組み立ててプロジェクトをマネージする責任の大きいミッションに、今は夢中で取り組んでいます。
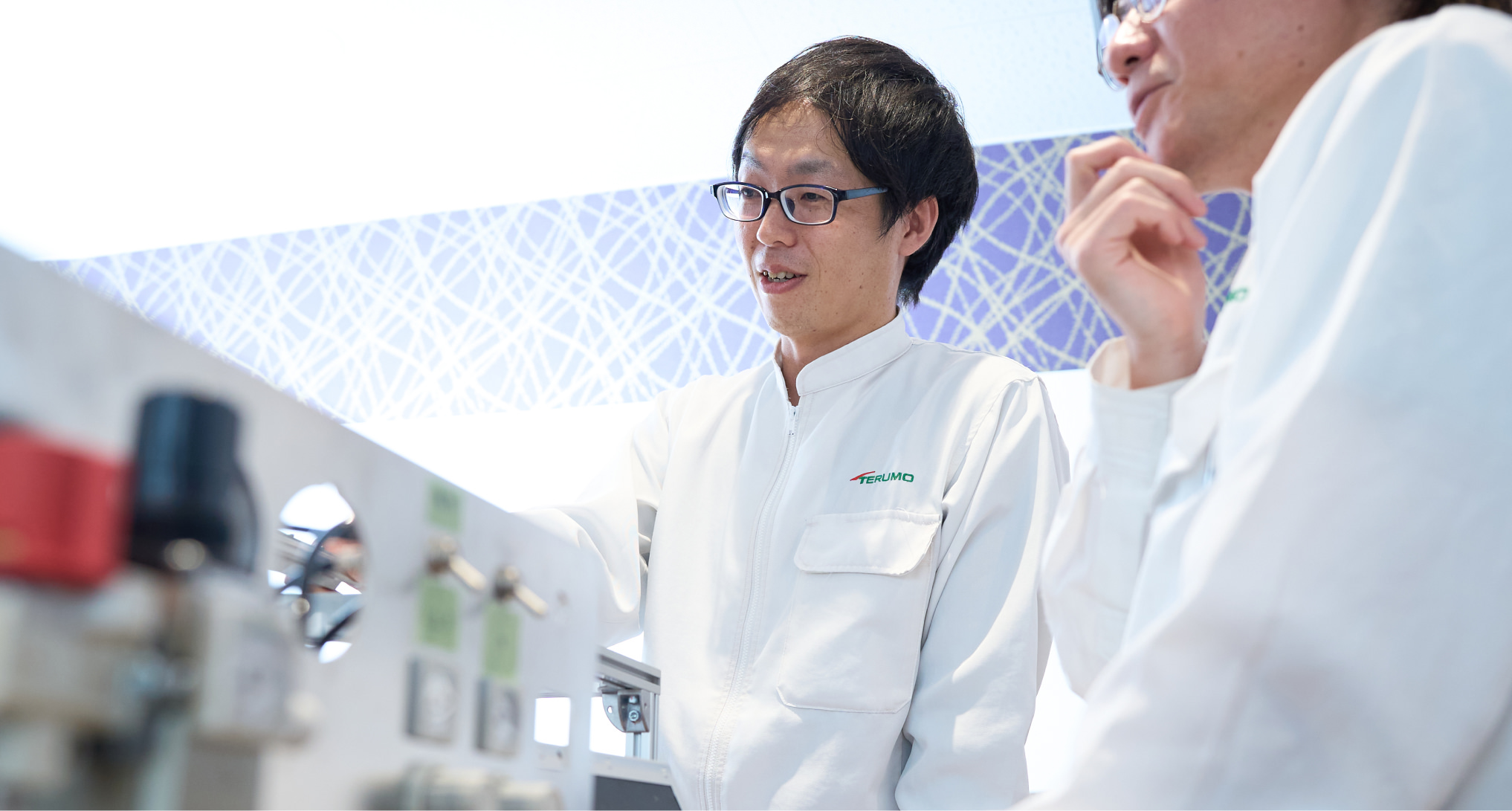
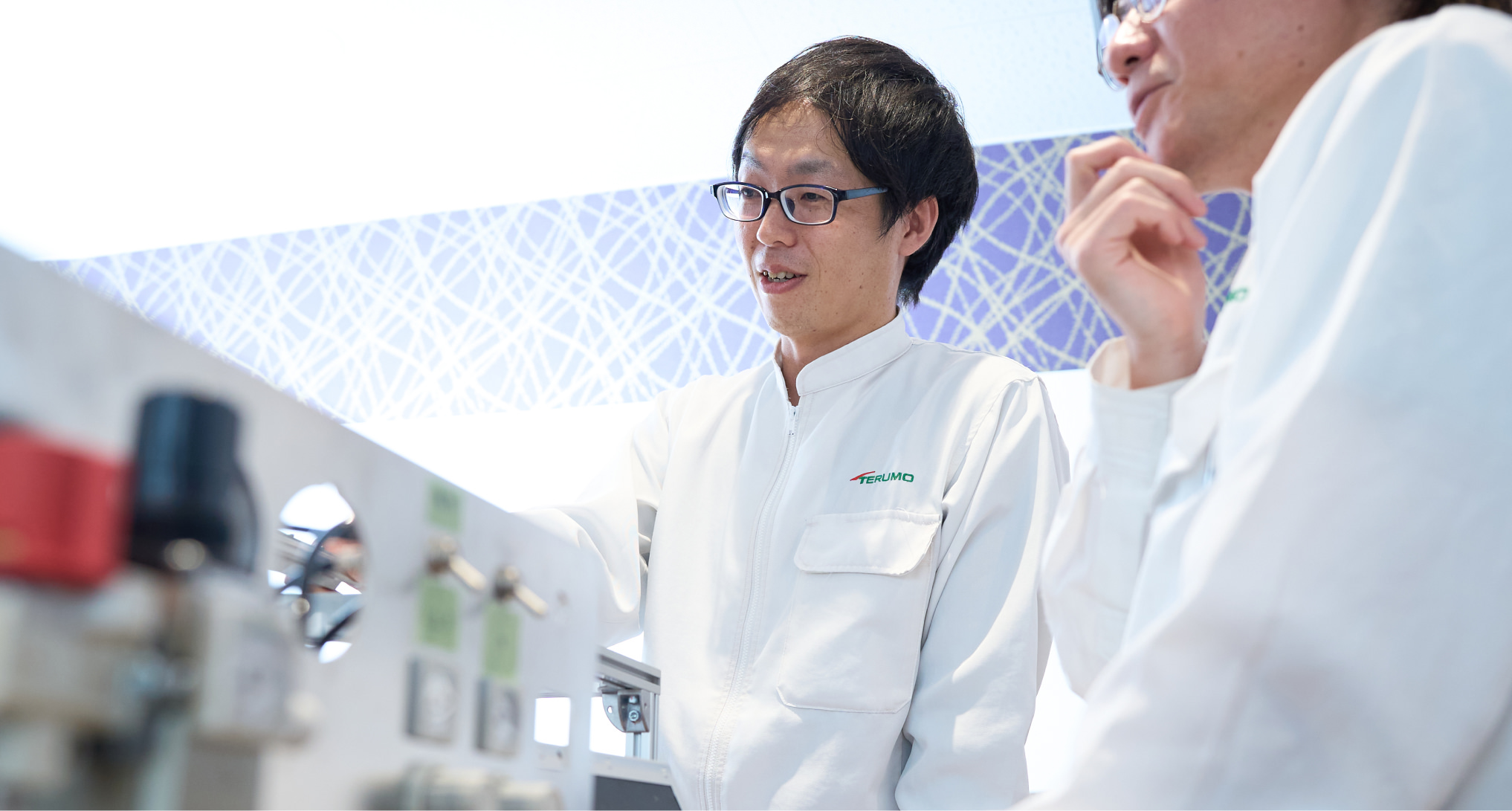

プロジェクトマネジメント経験を活かし、
生産効率の大幅な向上に寄与する。
前職で身につけた、効率的な設備工程のプロセス管理に必要な統計・データ解析技術や、生産設備・工程に必要なレギュレーション、バリデーション(有効性の検証)、監査・査察への対応などのスキルは、入社以来、さまざまな業務に役立てきました。たとえば、当社の主力となるカテーテル製品の生産設備・工程の立ち上げで、初めてプロジェクトリーダーを担った時は、工程立ち上げの条件設定に統計の手法やデータ解析法を導入し、効率性・安定性を兼ね備えた、堅牢な工程設計による生産設備の立ち上げに挑みました。そうした手法を取り入れることで、原材料劣化などの変質を管理でき、製品不良率の大幅な低減が期待できます。結果的に、通常1年程度かかる設備の立ち上げを半年に短縮。安定的な品質管理も実現し、生産効率が大幅に向上しました。これは培った経験を結果につなげた最初の成功体験でしたが、現在取り組んでいる“スマートファクトリー化”のモデルケースでも同様に経験を活かし、プロジェクトに取り組んでいるところです。

より広い視野、高い視座が求められる
マネジメント職に挑戦していきたい。
今後の目標として、まずは目前に迫る「スマートファクトリー化」を形にし、国内外の生産拠点へのモデル展開に道筋をつけたいと考えています。それと併行して動き出しているプロジェクトが、新商品の生産設備立ち上げです。超微細なパーツや特殊な材料で構成される製品を、新たな生産設備で量産化するには多くのハードルがあります。しかし今回のプロジェクトは、その生産ノウハウを私たち愛鷹工場のものにする貴重な機会。これまで積み重ねた経験に自信を持ち、取り組んでいきたいと考えています。
テルモに転職してつくづく良かったと思うのは、技術者としての幅を大きく広げられたという成長実感があること。今はさらに現場をマネージする経験も重ねたことで、より広い視野、高い視座が必要なマネジメント職への興味も湧いています。そのため現在担当する複数のプロジェクトで結果を出し、ゆくゆくはそうしたポジションにもチャレンジしていきたいと考えています。
